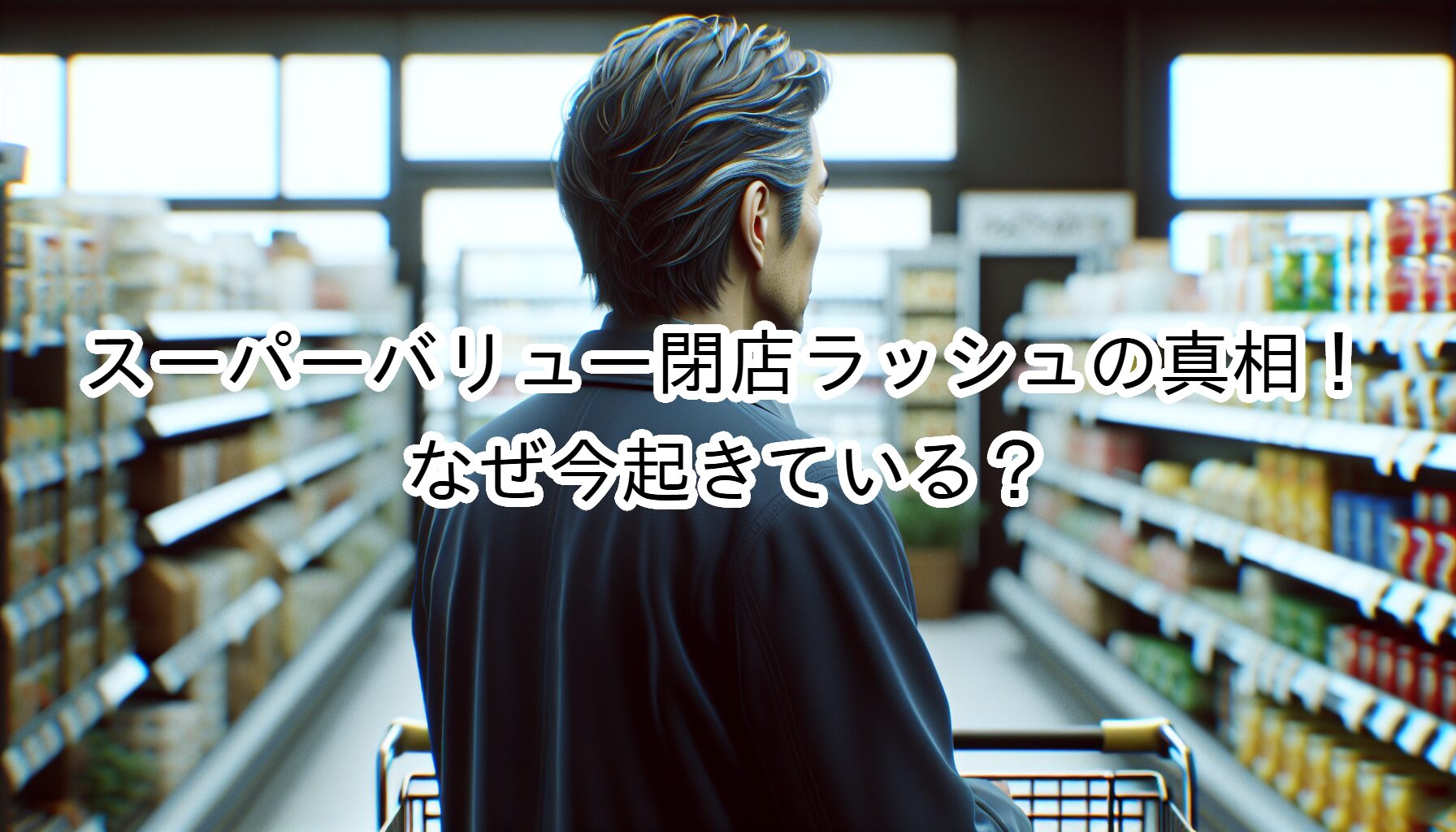「近所のスーパーバリューが閉店してしまったけど、これからどこで買い物をすればいいんだろう…」
「他の店舗もどんどん閉店していくのかな、経営が心配だ…」と不安に感じている方もいるのではないでしょうか。
生活に身近なスーパーマーケットだけに、相次ぐ閉店のニュースは気になりますよね。
この一連の閉店の背景には、実は見過ごせない理由が存在するのです。
この記事では、スーパーバリューの閉店ラッシュに不安を感じている方に向けて、
– なぜ今、閉店が相次いでいるのかという本当の理由
– 現在も営業している店舗と閉店した店舗の情報
– 親会社との関係から見る今後の展望
上記について、詳しく解説しています。
突然の閉店に戸惑う気持ちは、筆者もよく理解できます。
この記事を最後まで読めば、閉店が続く背景がすっきりと分かり、あなたの疑問や心配も解消されるでしょう。
ぜひ参考にしてください。
スーパーバリュー閉店ラッシュの背景を探る
近頃、スーパーバリューの店舗が次々と閉店していることに、驚きや不安を感じている方もいるかもしれません。
この一連の閉店は、単なる経営不振ではなく、親会社であるロピアホールディングスによる事業戦略の一環として進められているのです。
スーパーマーケット業界は、競争の激化や消費者のニーズの多様化など、大きな変化の時代を迎えています。
このような状況で勝ち残っていくため、企業は得意な分野に力を集中させ、より効率的な経営を目指す必要がありました。
今回の閉店は、グループ全体の力を最大限に発揮するための、未来に向けた前向きな判断といえるでしょう。
閉店の背景には、親会社との関係性や業界全体の構造変化など、複数の要因が複雑に絡み合っています。
以下で詳しく解説していきます。
ロピアやオーケーの影響力とは?
近年、関東地方を主戦場とするスーパーマーケット業界では、価格競争が熾烈を極めています。その中で特に存在感を放っているのが、「ロピア」と「オーケー」でしょう。両社は「高品質・Everyday Low Price」を掲げ、徹底したコスト削減と魅力的な商品戦略で消費者の絶大な支持を獲得しました。例えば、ロピアは元精肉店ならではの鮮度と価格を両立した肉製品が人気を博し、オーケーはオネスト(正直)カードで商品の情報を正直に伝える姿勢も評価されています。こうした強力なディスカウントストアの出店は、周辺の既存スーパーにとって大きな脅威となるのです。特に価格面で太刀打ちできない店舗は顧客を奪われ、経営状況が悪化し、結果として閉店へと追い込まれるケースが少なくありません。この激しい消耗戦が、スーパーバリューが直面する閉店ラッシュの大きな要因の一つと考えられます。
不採算店舗の整理が進む理由
スーパーバリューで店舗の閉鎖が相次ぐ背景には、親会社であるロピアの経営戦略が大きく影響しています。2022年12月にOICグループの傘下となって以降、祖業であったホームセンター事業を段階的に縮小し、強みを持つ食品スーパー事業へ経営資源を集中させる方針を打ち出しました。この「選択と集中」という経営判断により、採算の厳しいホームセンター単独店や、食品との併設でも相乗効果が薄い店舗の整理が加速している状況です。実際に2024年には、埼玉県の上尾愛宕店や越谷店などが閉店しました。これは単なる業績不振というだけでなく、企業全体の競争力を強化するための事業再構築の一環と捉えることができるでしょう。
ドラッグストアとネットスーパーの台頭
近年、スーパーバリューをはじめとする地域密着型スーパーマーケットの閉店が相次ぐ背景には、新たな競合の存在が大きく影響しています。その筆頭が、食品の取り扱いを強化したドラッグストアでしょう。かつては医薬品や日用品が中心でしたが、現在では生鮮食品や冷凍食品、総菜まで揃える店舗が増加しました。ウエルシアホールディングスやツルハホールディングスといった大手チェーンは、利便性を武器にスーパーの顧客層を着実に奪っています。
さらに、オンラインで注文し自宅に商品が届くネットスーパーの普及も見逃せません。特に、子育て世帯や高齢者を中心に利用が拡大しており、実店舗への来店客数を減少させる一因となっています。イオンやイトーヨーカドーといった大手スーパーは積極的にネットスーパー事業を強化しており、こうした消費行動の変化に対応できない店舗が厳しい状況に置かれているのです。この業態を超えた競争の激化が、スーパーマーケット業界の閉店ラッシュを加速させているといえるでしょう。
スーパーバリューの中途半端さが弱点に
スーパーバリューの弱点は、食品スーパーとホームセンターを融合させた店舗形態そのものにあるのかもしれません。この独自の業態は、かつては利便性の高さで評価されていました。しかし、近年では各分野に特化した強力な競合が登場したため、その立場が非常に中途半端なものになったのです。食品部門ではオーケーストアやロピアといった徹底した低価格を武器にするディスカウントストアに価格競争で劣ってしまう。一方のホームセンター部門では、カインズやコーナンのような圧倒的な品揃えと専門性を持つ大型専門店にはかないません。結果として、どちらの利用目的を持つ顧客にとっても決め手に欠ける存在となり、客足が遠のく一因になったと考えられます。この「どっちつかず」の状況が、2023年以降見られる閉店ラッシュの根本的な原因と言えるでしょう。
スーパーバリューの未来予測
相次ぐ閉店のニュースに、スーパーバリューの先行きを不安に思う方も多いでしょう。
しかし、同社は単に規模を縮小しているわけではなく、事業再生ADR制度を活用して経営の立て直しを図っている最中です。
未来が完全に保証されたわけではありませんが、生き残りをかけた具体的な一歩を踏み出している段階と言えます。
企業が存続するためには、出血を止めるための痛みを伴う改革が不可欠な場合があります。
今回の閉店ラッシュは、まさに不採算部門を整理し、経営体質を健全化させるための重要なプロセスなのです。
これは、未来の成長に向けた土台を固めるための、苦渋の決断だったに違いありません。
具体的には、2024年2月に事業再生ADRが成立し、金融機関からの支援体制が整いました。
今後は、支援を受けながら不採算店舗の閉鎖を進める一方、人気のディスカウントストア「ロピア」との協業による商品力強化など、収益力改善に向けた施策が実行されていく見込みです。
厳しい状況は続きますが、再生に向けた道筋は見え始めています。
出店戦略の見直しが必要な理由
近年スーパーバリューで相次ぐ閉店は、単なる業績不振ではなく、経営戦略の大きな転換が背景にあります。最大の要因は、2022年にディスカウントスーパー「ロピア」を運営するOICグループの完全子会社となったことでしょう。この資本提携により、グループ全体での事業再構築が加速しているのです。具体的には、ロピアの主導で不採算店舗の整理が進められており、2023年には杉並高井戸店、2024年に入ってからは江戸川大杉店や越谷店などが閉店となりました。これは、従来のホームセンター併設型店舗から、ロピアが得意とする食品スーパー事業へと経営資源を集中させるための「選択と集中」の一環と考えられます。厳しい競争環境を勝ち抜くため、より収益性の高い店舗網へと再編する、積極的な出店戦略の見直しが進んでいる状況です。
高付加価値型スーパーへの転換の可能性
スーパーバリューが厳しい経営状況を打開する一手として、高付加価値型スーパーへの転換が考えられるでしょう。例えば、高品質なプライベートブランド「SuperValue SELECT」の拡充や、デパ地下を彷彿とさせるような質の高い惣菜コーナーの強化は、顧客の満足度を高める一手となり得ます。近年、消費者は価格だけでなく、商品の品質や独自性を重視する傾向にあるため、この戦略は有効かもしれません。成城石井やライフといった競合が独自の価値提供で成功を収めているように、スーパーバリューもホームセンター併設という強みを活かし、食と暮らしを豊かにするユニークな提案で差別化を図ることが、生き残りの鍵を握るのではないでしょうか。
ECとの連携強化が鍵
ロピアの傘下で経営再建を進めるスーパーバリューですが、不採算店舗の閉店が続いており、厳しい状況にあります。 実店舗の立て直しと同時に、今後の成長戦略としてEC部門との連携強化が不可欠でしょう。スーパーバリューには、価格.comに出店し10年以上の運営実績を持つ通販サイト「SuperValueshopping」が存在します。 この既存のEC基盤を活用しない手はありません。親会社となったロピアの強みである、魅力的なプライベートブランド商品や圧倒的な価格競争力を持つ生鮮食品をオンラインで展開できれば、新たな顧客層の獲得につながるはずです。競合他社がネットスーパーでシェアを拡大している現状を踏まえると 、実店舗とECを連携させたオムニチャネル化を推し進めることが、閉店ラッシュから抜け出すための重要な一手となるのではないでしょうか。
再編・買収・提携の可能性
スーパーバリューは現在、大規模な事業再編の真っただ中にあります。2022年7月、ディスカウントスーパー「ロピア」を中核とするOICグループ(当時のロピア・ホールディングス)と資本業務提携を締結し、同年8月には第三者割当増資を経てその傘下に入りました。 この動きは、経営状況が厳しかったスーパーバリューの再建を目的としたものです。相次ぐ閉店は不採算店舗の整理という再編の一環であり、その一方でロピアの強みである生鮮食品のノウハウやプライベートブランド商品を導入した店舗改装が進められています。 物流網の共同利用によるコスト削減といったシナジー効果も追求しており、OICグループとの提携によって財務体質の改善と商品力の強化を図り、競争が激しい首都圏での生き残りをかけた挑戦を続けているのです。
地域密着型の再構築でブランド再生へ
近年、閉店が相次いでいたスーパーバリューですが、2022年にロピアなどを展開するOICグループの傘下に入り、経営再建を進めています。 この再建計画の柱となるのが、ロピア流の「個店主義」を取り入れた店舗改革と、地域に根差したサービスの強化です。 具体的には、各店舗の裁量を増やして地域特性に合わせた品揃えを実現したり、ロピアの強みである高品質な生鮮食品やプライベートブランド商品を投入したりすることで、顧客満足度の向上を目指しています。 リニューアルオープンした店舗では、生鮮食品の売り場を拡充するなど、専門性を高めた売り場作りが特徴的です。 これまで画一的だった店舗運営から脱却し、それぞれの地域で最も支持される店作りを目指すことで、ブランドイメージの刷新と業績の回復を図っていく考えです。
スーパーバリュー閉店に関するよくある質問
スーパーバリューの閉店が続くと、「私の家の近くの店舗は大丈夫?」や「貯めたポイントはどうなるの?」といった不安や疑問を感じる方もいるでしょう。
ここでは、そんなあなたの疑問に一つひとつお答えしていきます。
長年利用してきた店舗がなくなるのは、寂しい気持ちになりますよね。
食料品や日用品の買い物など、日々の生活に密着しているスーパーだからこそ、閉店の影響は大きいものです。
不確かな情報に惑わされず、正しい情報を知ることが大切になります。
具体的には、「閉店セールの予定は?」「残ったポイントカードの扱いはどうなる?」といった実用的な質問から、「従業員の方々の今後はどうなるのか」といった心配の声まで、さまざまな疑問が寄せられています。
これらのよくある質問に対して、分かりやすく解説します。
スーパーバリューの跡地利用はどうなる?
スーパーバリューの閉店が相次ぐ中、跡地の活用方法に注目が集まっています。2022年8月にロピアを運営するOICグループの傘下に入ってから、不採算店舗の整理が進む一方、リニューアルオープンする店舗も出てきました。 具体的な跡地利用としては、親会社であるロピアが新たに出店するケースが考えられます。実際に、ロピアはスーパーバリューの元店舗を改装し、「ロピア」としてオープンさせることで首都圏での店舗網を拡大する戦略をとっています。 また、スーパーバリューが食品スーパーに特化する方針を打ち出しているため、ホームセンターだった区画には「コーナンPRO」など、別のテナントが入居する事例もあります。 例えば、上尾緑丘店の跡地にはコーナンPROが出店しました。 このように、閉店した店舗の立地や規模に応じて、様々な企業が跡地利用を検討している状況なのです。
赤字の原因は何だったのか?
スーパーバリューが赤字に陥った背景には、複数の要因が複雑に絡み合っていました。最大の要因として挙げられるのが、ドラッグストアやディスカウントストアといった異業種を含めた競合の激化でしょう。これらの店舗が食品分野へ積極的に進出したことで価格競争が熾烈になり、スーパーバリューの収益を大きく圧迫したのです。さらに、近年の原材料費や原油価格の高騰は、仕入れコストや物流費、水道光熱費を押し上げる結果を招きました。消費者の節約志向が強まる中で、これらのコスト上昇分を売価へ十分に転嫁することも難しかったと考えられます。こうした厳しい外部環境に加え、既存店の老朽化への対応といった内部的な課題も抱えていたようです。結果として、ロピアによる買収前の2023年2月期決算では、最終損益が約20億円の赤字という厳しい状況に追い込まれたのでした。
ロピアとの関係性について
スーパーバリューで相次ぐ店舗の閉店には、ディスカウントスーパー「ロピア」との経営戦略が大きく関わっています。2023年、株式会社スーパーバリューはロピアの親会社である株式会社ロピアホールディングスと資本業務提携を締結しました。この提携の一環として、スーパーバリューが展開してきた食品スーパー事業の28店舗を、同年9月1日付で株式会社ロピアへ譲渡するに至ったのです。この事業譲渡により、一部のスーパーバリュー店舗は閉店し、改装期間を経てロピアとして新たにオープンする流れとなりました。したがって、一連の閉店は事業不振によるものではなく、スーパーバリューが祖業であるホームセンター事業へ経営資源を集中させるための戦略的な判断だったといえるでしょう。
大泉店のその後について
スーパーバリュー練馬大泉店は、2024年8月30日をもって閉店することが発表されました。 なお、食品フロアは先行して7月31日で営業を終了する予定です。 閉店の背景には、黒字店舗でありながらも近年は収益が減少傾向にあったことが挙げられます。 この店舗の土地と建物は、親会社であり「ロピア」などを運営するOICグループへ22億4400万円で売却されました。 スーパーバリューはこの売却で得た資金を、当面の運転資金や借入金の返済に充当する計画だと説明しています。 気になる閉店後については、ロピアが新たに出店する見通しです。 既にスーパーバリューの公式サイト上では「ロピア練馬大泉店」として案内されており、改装を経てリニューアルオープンすることが確実視されている状況といえるでしょう。
まとめ:スーパーバリューの閉店ラッシュ、その背景とこれから
今回は、スーパーバリューの相次ぐ閉店に不安を感じている方に向けて、
– 閉店ラッシュの具体的な状況
– なぜ今、閉店が続いているのかという理由
– スーパーバリューの今後の事業展開
上記について、解説してきました。
スーパーバリューの閉店ラッシュは、経営戦略の転換が大きな要因です。
競争の激化する食品スーパー事業から撤退し、強みを持つホームセンター事業へ資源を集中させるという、未来を見据えた判断が下されました。
長年親しんだお店がなくなることに、寂しさや戸惑いを感じている方も少なくないでしょう。
この変化の背景を知ることで、ただ閉店を惜しむだけでなく、今後の動きにも目を向けることができます。
閉店セールの情報を確認したり、新しいお気に入りの店を探したりと、前向きな行動につなげていきましょう。
これまでスーパーバリューを利用してきた時間は、決して無駄ではありません。
日々の買い物を通じて、あなたの生活はもちろん、地域を支えてきたという事実は確かなものです。
企業は常に変化し成長していく存在でした。
スーパーバリューが新たな形でサービスを提供する未来や、これを機に新しいお店と出会える可能性も十分に考えられます。
まずは、スーパーバリューの公式情報に注目しつつ、あなたの街の新しい魅力を探してみてはいかがでしょうか。
今回の変化をきっかけに、買い物がより豊かなものになるよう、筆者も応援しています。